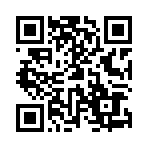2020年03月29日
東陣のさくら アラカルト
今日はあまりお天気がよくありませんでしたが
機会を逃しては撮れませんので
西陣ではなく「東陣」のさくらをご紹介していきます
まずは、堀川今出川のさくら

次は白峯神宮の左近乃桜

それから報恩寺境内のさくら

そして妙顕寺境内のさくら

そして寺の内小川の百々橋の公園のさくら

そして本法寺のさくら

そして妙覚寺のさくら

そしてそして最後は水火天満宮の枝垂れ桜

どうでしたか?ほんとに急いでご紹介した「東陣」のさくら
ここで!私は堀川通りよりも東は敵陣「東陣」と呼びます
よくこの紹介しました地域も「西陣」と称して紹介されますが
「違います!」(私見)西陣と一緒にしないでください。
それと、神社は別としてお寺は全て日蓮宗です
西陣は比較的日蓮宗のお寺が多い地域なんです
特に理由はないと関係者の見解でした
また、日蓮宗の境内は花の咲く草木が多い傾向があります
そのあたりが庶民に親しまれ信仰を厚くしたとも思考します
対して禅宗のお寺(大徳寺など)は修行に偏重した武士面で
修行に集中する為に侘び寂を重んじたと思考しています。
さくらひとつを見ても傾向が伺えます
あ~、きれいやな~、で、終わらず
なんでさくらが咲いているのか?
ほんまにどおでもええ事を追求する事に深さを感じています
2016年03月01日
あさが来た!
有料国営放送局の朝の連続ドラマ「あさが来た」の
主人公、広岡浅子の生誕の地が西陣の近くにあります。
現在は「ルビノ京都堀川」という公立学校共済組合宿泊所の
施設が建ていますが当時、庭にあった石燈籠や
手水鉢などが残されています。
京都の三井家は、御所に近い出水にあるところから
「出水三井」といわれていました。
御所や二条城の近くには、北家、南家をはじめ
三井各家が集まっていたそうです。

京都本邸の敷地の広さは、敷地は1389坪、
建物は木造瓦葺7棟333坪。
京都本邸は戦災では焼失を免れました。

出水三井家の住所は「上京区堀川通下長者町下ル三丁目7番と
同区油小路通出水上ル大黒屋町34の2だったそうです。

2015年01月08日
三方・電柱仁丹
よく通る道で見落としていたものがありました。

どこにでもある四つ角なんですが・・・
ふと見上げると仁丹の住所表示板があった!

1枚ならどこにでもある
偶然にも向かいの軒下にもあった!

ここまではよくある!
が、しかし・・・
その向かいの電柱に・・・
仁丹の看板が括られてあった!!!

三方に仁丹の住所表示板がある辻はそうない!
三方仁丹?そして、電柱に括られてるのは電柱仁丹?
と名付けましょう?(仁丹楽会さんすんません!)
では「京(今日)の一曲」は
「冬の色」 山口百恵さんでお聴きください
どこにでもある四つ角なんですが・・・
ふと見上げると仁丹の住所表示板があった!
1枚ならどこにでもある
偶然にも向かいの軒下にもあった!
ここまではよくある!
が、しかし・・・
その向かいの電柱に・・・
仁丹の看板が括られてあった!!!
三方に仁丹の住所表示板がある辻はそうない!
三方仁丹?そして、電柱に括られてるのは電柱仁丹?
と名付けましょう?(仁丹楽会さんすんません!)
では「京(今日)の一曲」は
「冬の色」 山口百恵さんでお聴きください
2014年09月27日
宮川町
今日は、少し西陣を離れ宮川町へ。
お彼岸に墓参りが出来ず今日、菩提寺へ行きました。
その通り道に宮川町があります
ちょうどお昼、この界隈ではまだこれから?
と、いう時間ですが、それはそれなりに風情があるものですが
今日は、お茶屋さんには目を向けず
宮川町を訪れる方に目を向けてみました。
まずは、コレ! なんちゃって舞妓?
そんな言い方は失礼ですね、コスプレ?
これまた失礼! 舞妓体験ですね!
ちょうど着付けられたとこらしく記念撮影されてました。

次は、人力車で宮川町にお越しのカップル?
ちょっとご年配ですが・・・
熱心にお兄さんの説明を聞いておられました。

これだけでは宮川町の雰囲気が出ない?
ならば! これでどうでしょうか?
白木の格子。

そして、焼き入れた板塀。

この界隈、歩くと純和風?を感じました。
では「京(今日)の一曲」は
発想が単純ですんません!
「京都慕情」 渚ゆう子さんでお聴きください。
お彼岸に墓参りが出来ず今日、菩提寺へ行きました。
その通り道に宮川町があります
ちょうどお昼、この界隈ではまだこれから?
と、いう時間ですが、それはそれなりに風情があるものですが
今日は、お茶屋さんには目を向けず
宮川町を訪れる方に目を向けてみました。
まずは、コレ! なんちゃって舞妓?
そんな言い方は失礼ですね、コスプレ?
これまた失礼! 舞妓体験ですね!
ちょうど着付けられたとこらしく記念撮影されてました。
次は、人力車で宮川町にお越しのカップル?
ちょっとご年配ですが・・・
熱心にお兄さんの説明を聞いておられました。
これだけでは宮川町の雰囲気が出ない?
ならば! これでどうでしょうか?
白木の格子。
そして、焼き入れた板塀。
この界隈、歩くと純和風?を感じました。
では「京(今日)の一曲」は
発想が単純ですんません!
「京都慕情」 渚ゆう子さんでお聴きください。
2013年11月17日
ポン!
今日はええお天気の日曜日でした!
明日、媒酌人の大役を控え新郎・新婦と懇談したり
司会や2次会の幹事と打ち合わせしたりで
つい先程、やっと終わり本業は開店休業状態でした
しかし、ブログの更新はせんならん!
さて、困ったネタがない!
ことはありません!
今日は「西陣」を少し離れて京都の繁華街を代表する
「先斗町」をご紹介してみましょう
先斗町(ぽんとちょう)は京都市中京区に位置しする
鴨川と木屋町通の間にある花街です
「町」と付いてますが地名としての先斗町はありまへん!
しかし、先斗町通については「先斗町通四条上る柏屋町」等
公文書に使用されています

もともとは鴨川の州で江戸時代初期の寛文10年(1670年)に
護岸工事で埋立てられ新河原町通と呼ばれていました
繁華街としては茶屋、旅籠などが置かれたのが始まりで
芸妓、娼妓が居住するようになり、何度も取り締りを受けましたが
川端二条にあった『二条新地』(にじょうしんち)の出稼ぎ地として
認められ明治初期に独立しました
そして、明治5年(1872年)に鴨川をどりが初演され
先斗町は花街としての花を開かせました

三条通一筋下ルから四条通まで鴨川と木屋町通の間を
南北に走る石畳の狭い通りです
花街特有の商業形態の他、一般の飲食店も並び通り東側の店は
鴨川に面し納涼床を設ける飲食店が多くあります
先斗町歌舞練場は北の端にあり鴨川に大きな姿を映します

地名は一説によれば先斗という地名の語源はポルトガル語の
ponto(「先」の意)にあるとされています
しかし、正しいポルトガル語は"PONTA"なのに「ポント」と
読まれることや、なぜ「先斗」の字があてられたのかなどが
謎とされています
また、鴨川と高瀬川の2本の川に挟まれていることを
2枚の皮に挟まれている鼓にたとえ、鼓の「ポン」と鳴る音に掛けて
「ぽんと」となったという説もあるそうです

四条通より南側に続く通り(下京区)を先斗町と呼んでも
理解されますが、正しくは西石垣通(さいせきどおり)という
別の名前があり、繁華街が続いています
ここには鴨川の氾濫を防ぐために造られた石垣が今も残っています
そこで、私は先斗町とおえばココ!を
ご紹介したいところがあります
ここは「一力」・「一力茶屋」とも云われているところ
「忠臣蔵」の大石内蔵助が遊んだお茶屋としてよく知られています
もともと「万屋」と称しており、仮名手本忠臣蔵に登場し
一躍その名が世にしられるようになったお茶屋です
店名の「一力」という店の名は、維新前は「万屋」が屋号でしたが
後に「万」の字を「一」と「力」に分け「一力亭」に変えましたが
その経緯は芝居の影響で変わったそうです

今でも門の中の入り口には「万」の字の暖簾がかかっています!
「一力」だが、暖簾の文字は「万」です
幕末時代に至っても政治の場であった「一力茶屋」は
元治2年(1865)祇園に大火があったとき「一力茶屋」も被災し
その後に再建され100余年を経ています

日頃、静かな西陣の街を駆け回っていると
たくさんの飲食店や人通りに驚きを隠せません
西陣にも「西陣京極」や「上七軒」がありますが
少し寂しさを感じずにはいられないのが本音です
さてさて、明日はとうとう結婚式・披露宴で媒酌人を務めます
あと12時間余りとなりましたが
式は厳かに!披露宴は笑いと涙で!
新郎・新婦は待ち遠しいでしょうが
私は早く終わらないものかと・・・
とにかく無事に無事に終わればそれで良し
こんな「玉」突いてる場合やなかったんですが
つい夕方、新郎・新婦と突いてきました

新婦が女子部へ入部したのが6年前
新郎は10年くらい前におっさん組に入りました
どちらも最初は「遊び」で続かんやろ?
と、思ってましたが、意に反して練習熱心で
いろいろと教えたことくらいしか印象にないのですが
両人にしてみれば面倒見が一番良かったと云ってます
ん~、特別に意識したことはなかったのですが・・・
新郎は「素直」、新婦は「やさしい」と感じました
まぁ、所帯を持てば今の気持ちは徐々に薄れますが
二人をこれまで見る限り大丈夫だろう?
いい家庭を作ることが出来るだろう?
ここ最近、そう思うようになって来ました
二人に幸多かれと願うばかりです
では、「京(今日)の一曲」は
「お座敷小唄」を和田弘とマヒナスターズでお聴きください
明日、媒酌人の大役を控え新郎・新婦と懇談したり
司会や2次会の幹事と打ち合わせしたりで
つい先程、やっと終わり本業は開店休業状態でした
しかし、ブログの更新はせんならん!
さて、困ったネタがない!
ことはありません!
今日は「西陣」を少し離れて京都の繁華街を代表する
「先斗町」をご紹介してみましょう
先斗町(ぽんとちょう)は京都市中京区に位置しする
鴨川と木屋町通の間にある花街です
「町」と付いてますが地名としての先斗町はありまへん!
しかし、先斗町通については「先斗町通四条上る柏屋町」等
公文書に使用されています
もともとは鴨川の州で江戸時代初期の寛文10年(1670年)に
護岸工事で埋立てられ新河原町通と呼ばれていました
繁華街としては茶屋、旅籠などが置かれたのが始まりで
芸妓、娼妓が居住するようになり、何度も取り締りを受けましたが
川端二条にあった『二条新地』(にじょうしんち)の出稼ぎ地として
認められ明治初期に独立しました
そして、明治5年(1872年)に鴨川をどりが初演され
先斗町は花街としての花を開かせました
三条通一筋下ルから四条通まで鴨川と木屋町通の間を
南北に走る石畳の狭い通りです
花街特有の商業形態の他、一般の飲食店も並び通り東側の店は
鴨川に面し納涼床を設ける飲食店が多くあります
先斗町歌舞練場は北の端にあり鴨川に大きな姿を映します
地名は一説によれば先斗という地名の語源はポルトガル語の
ponto(「先」の意)にあるとされています
しかし、正しいポルトガル語は"PONTA"なのに「ポント」と
読まれることや、なぜ「先斗」の字があてられたのかなどが
謎とされています
また、鴨川と高瀬川の2本の川に挟まれていることを
2枚の皮に挟まれている鼓にたとえ、鼓の「ポン」と鳴る音に掛けて
「ぽんと」となったという説もあるそうです
四条通より南側に続く通り(下京区)を先斗町と呼んでも
理解されますが、正しくは西石垣通(さいせきどおり)という
別の名前があり、繁華街が続いています
ここには鴨川の氾濫を防ぐために造られた石垣が今も残っています
そこで、私は先斗町とおえばココ!を
ご紹介したいところがあります
ここは「一力」・「一力茶屋」とも云われているところ
「忠臣蔵」の大石内蔵助が遊んだお茶屋としてよく知られています
もともと「万屋」と称しており、仮名手本忠臣蔵に登場し
一躍その名が世にしられるようになったお茶屋です
店名の「一力」という店の名は、維新前は「万屋」が屋号でしたが
後に「万」の字を「一」と「力」に分け「一力亭」に変えましたが
その経緯は芝居の影響で変わったそうです
今でも門の中の入り口には「万」の字の暖簾がかかっています!
「一力」だが、暖簾の文字は「万」です
幕末時代に至っても政治の場であった「一力茶屋」は
元治2年(1865)祇園に大火があったとき「一力茶屋」も被災し
その後に再建され100余年を経ています
日頃、静かな西陣の街を駆け回っていると
たくさんの飲食店や人通りに驚きを隠せません
西陣にも「西陣京極」や「上七軒」がありますが
少し寂しさを感じずにはいられないのが本音です
さてさて、明日はとうとう結婚式・披露宴で媒酌人を務めます
あと12時間余りとなりましたが
式は厳かに!披露宴は笑いと涙で!
新郎・新婦は待ち遠しいでしょうが
私は早く終わらないものかと・・・
とにかく無事に無事に終わればそれで良し
こんな「玉」突いてる場合やなかったんですが
つい夕方、新郎・新婦と突いてきました

新婦が女子部へ入部したのが6年前
新郎は10年くらい前におっさん組に入りました
どちらも最初は「遊び」で続かんやろ?
と、思ってましたが、意に反して練習熱心で
いろいろと教えたことくらいしか印象にないのですが
両人にしてみれば面倒見が一番良かったと云ってます
ん~、特別に意識したことはなかったのですが・・・
新郎は「素直」、新婦は「やさしい」と感じました
まぁ、所帯を持てば今の気持ちは徐々に薄れますが
二人をこれまで見る限り大丈夫だろう?
いい家庭を作ることが出来るだろう?
ここ最近、そう思うようになって来ました
二人に幸多かれと願うばかりです
では、「京(今日)の一曲」は
「お座敷小唄」を和田弘とマヒナスターズでお聴きください
2013年10月08日
豊国神社(その界隈)
また台風が来てますね、その影響かなんだか蒸し暑い
さて、豊国神社・方広寺をご覧頂きました
しかし、まだこの界隈には気になるところがありました。
豊国神社、通りを挟んで向かい側に
小高い丘のような天辺に石の塔が建っている
なんやこれ?

古墳?と思って近くを通ったことがあるのですが
正体を確認しに行きました
構えからして古墳ぽい?

立札に「耳塚」と記されています
「塚」!? まぁ、お墓みたいなもんか!

と読みはじめたら・・・
豊臣秀吉の朝鮮出兵のうち、慶長の役で戦功の証として
討ち取った朝鮮・明国人の耳や鼻を削ぎ持ち帰ったものを
葬った塚らしい
当時は戦功の証として敵の高級将校は死体の首をとっていましたが
農民軍や足軽など身分の低いものは鼻(耳)でその数を証した
(これをしないことを打捨と言われていました)
運搬中に腐敗するのを防ぐために、塩漬、酒漬にして持ち帰りました
そして検分が終われれば、戦没者として供養しその霊の災禍を防ぐのが
古来よりの日本の慣習であり、丁重に供養されたました
昭和44年「方広寺石塁および石塔」として国の史跡に指定された
当初は「鼻塚」と呼ばれていたが林羅山の著書『豊臣秀吉譜』の中で
鼻そぎでは野蛮だというので「耳塚」と書いて以降
耳塚という呼称が広まったそうです
なんと!2万人分の耳と鼻が埋められているそうです!
周囲の石柵は歌舞伎役者をはじめとする
当時の著名芸人達の寄付によって建立された物で
発起人は京都の侠客「伏見の勇山」と伝えられ
塚前の焼香台・石段も寄贈したそうです
戦といえど酷い事をしたもんだ・・・
耳や鼻を削ぎ取るなんて人間のする事か?
当時のことだ、「国益」や「防衛」の戦争ではなかったろう
ただ領地を広げ地位を築くだけだろう
こんな供養塔を建てるくらいなら戦をしなければええのに・・・
と思い「耳塚」を後にしました。
で、ここはこんな所!
現在、東山区ですが表示は「下京区」
で、通り名は「大黒町通り」、なんだか親近感が湧いてきた。

看板の向かいには昔のまんまの酒屋さんがありました
(自販機がちょっと風情をなくしますが・・・)

こんな看板、今は作られてるのかな?

ビールの看板もありますね!

月桂冠もありました!

七条通りへと歩いていたら
まぁ、近くが清水焼の産地ちゅうこともありますね!
作り立ての器が干されてました

豊国神社の周辺を少し探検しました
近くには博物館や三十三間堂など観光名所があります
ちょっと路地に入ったりするだけで
新たな発見や再認識がありました
京都に住んでまだまだ知らない事がありました
やっぱり京都は奥が深い!
では「京(今日)の一曲」は
松崎しげるさんで「愛のメモリー」をお聴きください。
さて、豊国神社・方広寺をご覧頂きました
しかし、まだこの界隈には気になるところがありました。
豊国神社、通りを挟んで向かい側に
小高い丘のような天辺に石の塔が建っている
なんやこれ?
古墳?と思って近くを通ったことがあるのですが
正体を確認しに行きました
構えからして古墳ぽい?
立札に「耳塚」と記されています
「塚」!? まぁ、お墓みたいなもんか!
と読みはじめたら・・・
豊臣秀吉の朝鮮出兵のうち、慶長の役で戦功の証として
討ち取った朝鮮・明国人の耳や鼻を削ぎ持ち帰ったものを
葬った塚らしい
当時は戦功の証として敵の高級将校は死体の首をとっていましたが
農民軍や足軽など身分の低いものは鼻(耳)でその数を証した
(これをしないことを打捨と言われていました)
運搬中に腐敗するのを防ぐために、塩漬、酒漬にして持ち帰りました
そして検分が終われれば、戦没者として供養しその霊の災禍を防ぐのが
古来よりの日本の慣習であり、丁重に供養されたました
昭和44年「方広寺石塁および石塔」として国の史跡に指定された
当初は「鼻塚」と呼ばれていたが林羅山の著書『豊臣秀吉譜』の中で
鼻そぎでは野蛮だというので「耳塚」と書いて以降
耳塚という呼称が広まったそうです
なんと!2万人分の耳と鼻が埋められているそうです!
周囲の石柵は歌舞伎役者をはじめとする
当時の著名芸人達の寄付によって建立された物で
発起人は京都の侠客「伏見の勇山」と伝えられ
塚前の焼香台・石段も寄贈したそうです
戦といえど酷い事をしたもんだ・・・
耳や鼻を削ぎ取るなんて人間のする事か?
当時のことだ、「国益」や「防衛」の戦争ではなかったろう
ただ領地を広げ地位を築くだけだろう
こんな供養塔を建てるくらいなら戦をしなければええのに・・・
と思い「耳塚」を後にしました。
で、ここはこんな所!
現在、東山区ですが表示は「下京区」
で、通り名は「大黒町通り」、なんだか親近感が湧いてきた。
看板の向かいには昔のまんまの酒屋さんがありました
(自販機がちょっと風情をなくしますが・・・)
こんな看板、今は作られてるのかな?
ビールの看板もありますね!
月桂冠もありました!
七条通りへと歩いていたら
まぁ、近くが清水焼の産地ちゅうこともありますね!
作り立ての器が干されてました
豊国神社の周辺を少し探検しました
近くには博物館や三十三間堂など観光名所があります
ちょっと路地に入ったりするだけで
新たな発見や再認識がありました
京都に住んでまだまだ知らない事がありました
やっぱり京都は奥が深い!
では「京(今日)の一曲」は
松崎しげるさんで「愛のメモリー」をお聴きください。
2013年10月07日
豊国神社(釣鐘編)
爽やかなちょっと暑かった月曜日でした
さて、昨日、勿体ぶって続きをご期待くださいとしました。
私も少し見識が広がり少しウンチクを語りたいと思います
昨日、訪れた豊国神社に隣接します「方広寺(ほうこうじ)」
てっきりここも豊国神社と思っていました
方広寺といえば釣鐘が有名です

この釣鐘は銅でできていまして
高さ4.2メートル重さ82.7トンの立派なもので
(10円玉、何枚できるかな?)

知恩院、東大寺の銅鐘と並んで
日本三巨鐘の一つに数えられています
82トンもあるだけに厚みもかなりな鐘ですね

鐘突き堂には大仏殿跡から出土した金具が
無造作に置かれていました。

それだけなら話しは平和に終われるのですが・・・
鐘銘に「国家安康 君臣豊楽」とあり
これが徳川家康を胴斬りするものとして
「鐘銘事件」に発展し豊臣家滅亡の発端になりました。

ここまでは日本史で勉強された方がほとんでですが・・・
淀君の幽霊?が出てるんです!!!
この鐘の内部、画像中央に白い雲のようなものがあります
よぉ~く見ると、淀君の横顔ではありませんか!!!

このような画像をお伝えして良いのか?悪いのか?
その後、私の身に異変は・・・別にありませんでしたぁ!
隅っこに映る鐘の案内をして頂いたおばさま
流暢な京都弁で釣鐘をご説明頂きました

明日は、この辺りの探索編をお届けいたします!
では「京(今日)の一曲」は
ダスティ・スプリングフィールドで「 この胸のときめきを」お聴きください
さて、昨日、勿体ぶって続きをご期待くださいとしました。
私も少し見識が広がり少しウンチクを語りたいと思います
昨日、訪れた豊国神社に隣接します「方広寺(ほうこうじ)」
てっきりここも豊国神社と思っていました
方広寺といえば釣鐘が有名です
この釣鐘は銅でできていまして
高さ4.2メートル重さ82.7トンの立派なもので
(10円玉、何枚できるかな?)
知恩院、東大寺の銅鐘と並んで
日本三巨鐘の一つに数えられています
82トンもあるだけに厚みもかなりな鐘ですね
鐘突き堂には大仏殿跡から出土した金具が
無造作に置かれていました。
それだけなら話しは平和に終われるのですが・・・
鐘銘に「国家安康 君臣豊楽」とあり
これが徳川家康を胴斬りするものとして
「鐘銘事件」に発展し豊臣家滅亡の発端になりました。
ここまでは日本史で勉強された方がほとんでですが・・・
淀君の幽霊?が出てるんです!!!
この鐘の内部、画像中央に白い雲のようなものがあります
よぉ~く見ると、淀君の横顔ではありませんか!!!

このような画像をお伝えして良いのか?悪いのか?
その後、私の身に異変は・・・別にありませんでしたぁ!
隅っこに映る鐘の案内をして頂いたおばさま
流暢な京都弁で釣鐘をご説明頂きました
明日は、この辺りの探索編をお届けいたします!
では「京(今日)の一曲」は
ダスティ・スプリングフィールドで「 この胸のときめきを」お聴きください