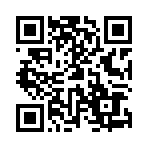2016年06月15日
2016年06月13日
本法寺「巴の庭」
日曜日、雨が降る前に本法寺へ行きました。
で、気分転換を兼ねて「巴の庭」を見ました

滅多に庭園なんて見ないのですが
竜安寺や色んな名園が京都にはありますが
ひっそりとした庭を眺めるのもいいもんで見入りました^^

詫びや寂の感じ方は人それぞれで
現実逃避かも知れませんが私は無の境地?になりました

光悦がどんな気持ちや表現をしているかは
私にはよくわかりませんが
それでいいのではなかと思います

また、気分や気持ちをそうさせる光悦恐るべし!
何百年も前に造られた庭が現在もそうさせるってスゴイ!

で、気分転換を兼ねて「巴の庭」を見ました
滅多に庭園なんて見ないのですが
竜安寺や色んな名園が京都にはありますが
ひっそりとした庭を眺めるのもいいもんで見入りました^^
詫びや寂の感じ方は人それぞれで
現実逃避かも知れませんが私は無の境地?になりました

光悦がどんな気持ちや表現をしているかは
私にはよくわかりませんが
それでいいのではなかと思います

また、気分や気持ちをそうさせる光悦恐るべし!
何百年も前に造られた庭が現在もそうさせるってスゴイ!

2016年06月09日
W仁丹
京都市内には明治から昭和初期の森下仁丹の
住所表示板が住宅の軒下に掲げられています。
近年、この看板を盗みオークションに出す輩がおり
上京署が捜査、警戒されて守られていますが
このように1軒の軒下に2枚も設置されているのは
大変珍しく住所表示の通りに面して住所を表記されています。
京都市内だけでしょうか通りを「上ル(あがる)下ル(さがる)」
として住所を表記し文字数にして16~18文字にもなる住所が
京都市内には存在します。
また、ひとつの住所の表記の仕方にも私の本籍地では
京都市北区紫野西藤の森町5番地
京都市北区智恵光院鞍馬口下ル西藤の森町5番地
2通りの表記方法があります。
が、住民票や戸籍謄本は先の行政区・町名・番地です。
わざわざ通り名を書くと長くなりますが
町名だけではどこらへんかわからない!
ので、通り名を書けばわかりやすい!
これが京都の心遣い?どすえ~^^
2016年06月07日
6月の今宮神社
あぶり餅屋のおばちゃんの熱い視線を感じながら
意を決して西門から撮ってみました
さて、境内は・・・、ほぼ貸し切り状態。
こんな機会は滅多とない!
本殿、南門、撮り放題。
私が子供の頃、母の実家が近かったもので
よくここへ遊びに来た時は、こんな感じだったんです
ふと、50年前(半世紀!)を思い出しました
そら私がおっさんになり、母もおばあちゃんになりますよね
しかし、変わらないのは今宮神社
境内は随分、きれいになりましたが
思い出はそのまんま変わらず。
さて、今宮神社の阿保賢さんは誰も知るところですが
他に境内には「力石(ちからいし)」があります。
鍛錬と娯楽にその昔は使われていたそうです
残念ながら今はコンクリートで固められて
持ち上げることはできません。
2016年06月04日
お土産~♪ お土産~♪
なんか西条凡児さんの素人名人会の出だしのようですが^^
急遽、東京から「散歩」に来られたお客さまが
「俵谷のもなかが食べたい!」と申されて
自転車で本店限定販売1個108円のもなかを買いに行きました。
京都の老舗和菓子店だけあってお上品なお菓子が
店内に置いてありました。
どう見ても庶民の3時のおやつじゃない!^^
あえて買えるならこのもなか!
だが、これまた値段とは真逆に美味い!
他では売ってまへんで!
ここと烏丸店・小川店しかありません!

あ!うちの分を買うの忘れてたぁ^^
2016年06月02日
西陣の大店
西陣の大店を撮ってみました。
すでに廃業されたところもありますが
佇まいは往時と変わりません

儲かればビルを建てたり辞めたら潰す昨今
西陣の大店はそんな事はしません
目先に捉われず次世代に引き継ぐ伝統があります

西陣で古くから続く織屋は派手を好まず質素です
大店と云えど職人である故でしょうか
威厳を保つと云えばわかりやすいでしょうか

画像の中には織屋の元祖があります
500年は続く大店があります
また、代々織物に専念し今日を築いたところもあります

副業に手を出すなど大店とは言えない
時代の流れと云い時流を追うのは邪道である
など、拘り抜いたものがあります

そんなところを「西陣は封建的だ」と揶揄されます
大店からすれば「言いたいものには言わせとけ」であり
伝統を引継ぎ後世に伝えるのが当代の役目と言われております
すでに廃業されたところもありますが
佇まいは往時と変わりません
儲かればビルを建てたり辞めたら潰す昨今
西陣の大店はそんな事はしません
目先に捉われず次世代に引き継ぐ伝統があります
西陣で古くから続く織屋は派手を好まず質素です
大店と云えど職人である故でしょうか
威厳を保つと云えばわかりやすいでしょうか
画像の中には織屋の元祖があります
500年は続く大店があります
また、代々織物に専念し今日を築いたところもあります
副業に手を出すなど大店とは言えない
時代の流れと云い時流を追うのは邪道である
など、拘り抜いたものがあります
そんなところを「西陣は封建的だ」と揶揄されます
大店からすれば「言いたいものには言わせとけ」であり
伝統を引継ぎ後世に伝えるのが当代の役目と言われております
2016年06月01日
町屋百選
スケッチの題材になった町屋です。
描かれた方はスケッチするだけでなく
その町屋について詳しく調べておられました。
看板を見ればどんなお商売をされているかわかります
それなら私のように「町屋です~」と紹介すればいい
しかし、それでは「あ~、そうですかぁ」で終わってしまう
現存する大きな町屋にはそれぞれ歴史があります。
築100年前後、明治、大正、昭和を経て
その時々の時代背景に左右されながら現在があります
画像の「西村医院」さんは元織物関係でした
従業員も抱え手広く商売をされていましたが
現在はお医者さん!らしくない佇まいです。なんでか?
建屋が広くて改装した方が経費が抑えられるからだとか
普通に建つ大きな町屋!で終わらさず
なんでかな?と、疑問を持てば見方も変わりますよ。